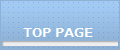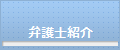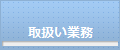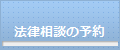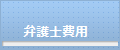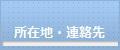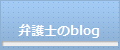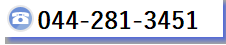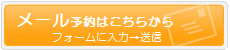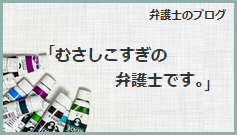離婚の手続
当事者の話合いで離婚が合意できれば、離婚届を役所に提出し、離婚成立となります(協議離婚)。しかし、親権や養育費、財産分与、慰謝料等で対立し、当事者の話合いでは離婚の合意ができないというケースはかなりあります。このような場合に、弁護士が代理で交渉をしたり、家庭裁判所の調停を利用することができます(離婚調停、審判、離婚訴訟)。それでは各手続について、以下で具体的にご説明します。
①協議離婚とは
②離婚の調停とは
③審判とは
④離婚訴訟とは
①協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦の話合いで離婚を合意することです。合意できれば、離婚届に必要事項を記入し、夫婦の他に成年の証人2名に署名・押印してもらい、離婚届を役所に提出します。 離婚にあたってお互いに約束しておきたい事項があれば、合意文書や公正証書の作成を検討されると良いでしょう。ご不明な点は、文書を取り交わす前に、弁護士にご相談ください。
離婚にあたってお互いに約束しておきたい事項があれば、合意文書や公正証書の作成を検討されると良いでしょう。ご不明な点は、文書を取り交わす前に、弁護士にご相談ください。
②離婚の調停とは
話合いでは離婚の合意ができない場合や、離婚すること自体はお互い納得していても、親権、養育費、財産分与、慰謝料等の離婚の諸条件で合意ができない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。調停は裁判所に申立書を提出するところからスタートします。申立書は原則として相手方に送付されるため、相手方に知られたくないようなことがある場合には、記載内容に注意して下さい。
裁判所が申立を受理すると、相手方に対して呼出状が送られます。
調停では調停委員が間に入り、申立人・相手方それぞれの言い分を整理して、合意に至る可能性を探ります。調停は、一か月に1回程度のペースで期日が入りますが、相手方が調停に来ない場合や、離婚の合意に達しないような場合には、調停不成立となります。調停不成立となった場合、次に進むためのステップは「離婚訴訟」となります。
 調停という手続は、弁護士を付けずに、ご本人だけでも対応可能ですが、相手方に弁護士が付いた場合や、離婚条件の交渉が難しい案件等、弁護士を付けた方が良い場合もあります。離婚調停の対応でお困りの方は、弁護士にご相談ください。
調停という手続は、弁護士を付けずに、ご本人だけでも対応可能ですが、相手方に弁護士が付いた場合や、離婚条件の交渉が難しい案件等、弁護士を付けた方が良い場合もあります。離婚調停の対応でお困りの方は、弁護士にご相談ください。
③審判とは
調停に付されている案件について、調停成立の見込みがない場合に、家庭裁判所は調停に代わる審判を行うことができます。審判になる場合とは、例えば離婚自体の合意はできたが、養育費等の諸条件で合意に至らない場合等です。ただし、審判に対してどちらか一方が異議を出せば、審判は効力がなくなるため、実際に審判が下されることはあまりありません。④離婚訴訟とは
調停では離婚の合意に至らず、調停が不成立で終了した場合、離婚について決着を付けるには、「離婚訴訟」を起こす必要があります。離婚訴訟では、それまでの調停などとは異なり、離婚の請求が認められるためには、法律が定める下記のような「離婚原因」が必要となります。
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
 離婚訴訟は調停とは異なり、主張は書面で行うのが基本なので、弁護士に依頼しないと大変です。武蔵小杉綜合法律事務所では、見通しや弁護士費用について、詳しくご説明しますので、離婚をお考えの方は当事務所の法律相談をご利用下さい。
離婚訴訟は調停とは異なり、主張は書面で行うのが基本なので、弁護士に依頼しないと大変です。武蔵小杉綜合法律事務所では、見通しや弁護士費用について、詳しくご説明しますので、離婚をお考えの方は当事務所の法律相談をご利用下さい。
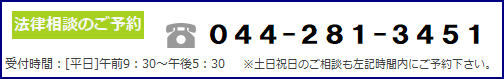
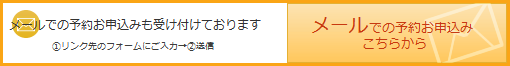
→離婚の相談トップページに戻る。
→トップページに戻る。